日本で使われる有機農法という言葉は、世界的な用語’オーガニック’と若干ニュアンスが違う使われ方をしているようにみえます。日本で使われる「有機・無農薬」というような言葉は、いくつかの矛盾を内包します。
ケンブリッジ大学の辞書によると、オーガニック(有機)とは、「食品およびその他加工食品を生産する植物あるいは動物の生育過程で人工的な化学物質を使わない事」="not using artificial chemicals in the growing of plants and animals for food and other products"と定義されています。
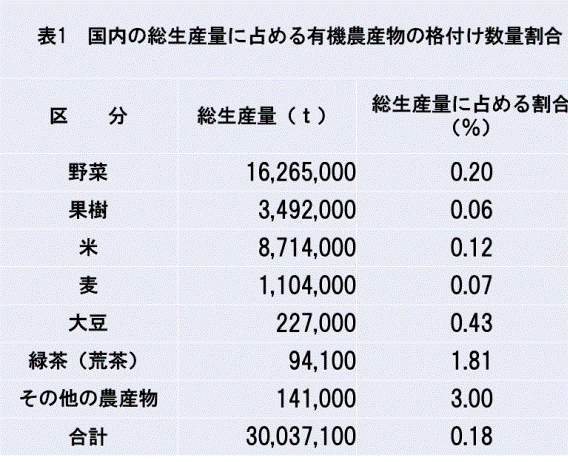
日本で「有機農産物」と表示するには、有機JAS規格(農林水産大臣が制定した「日本農林規格」)を満たさなければなりません。つまり「有機JASマーク」がなければ「有機栽培」ではありません。
農林水産省の「有機農業の推進について」という資料(表1に抜粋)によると、国内総生産量に占める有機農産物の割合は、平均0.18%と1%にも満たないのが現状のようです。個別作物では荒茶が1.81%で最も多く、野菜0.2%、米0.12%などとなっています。この平均0.2%ほどの数字は、若干の年次変動があってもほぼ一定しており、有機JAS農業の広がりはあまりない、というのが現状だと思われます。直売所などで「有機無農薬」という表示をよく見かけますが、「有機JASマーク」がついている農産物は少ないのではないでしょうか。
なぜ有機栽培が増えないのか。理由は様々あると思いますが、肉体労働の負担に比べて、せいぜい1-2割増でしか売れない現実が挙げられます。半自給自足的な家族経営が多いので、面積拡大が難しく、所得が思ったほどには伸びないのです。一方、子供が生まれればその成長につれて、貨幣経済との接点が増え、過剰な労働が強いられます。その結果、体への負荷が限界を超え、当初の理想と違う現実に直面して有機農業から離れるという、循環をよく聞きます。コンビニの数の増減に似た現象が潜在的にあるのではないでしょうか。
ヨーロッパ方面で、オーガニックが推奨される理由には、環境負荷軽減という視点が第一だと聞きます。一方、日本では多くの消費者が、「オーガニック=健康、安全」と人体への安全性を主に考えているように見受けられます。しかし、JAS規格には人体への安全性、健康への効果は一切書かれていません。あくまで消費者が抱く不正確なイメージであり、またそこに付加価値を見出そうという生産者の狙いも見え隠れしているように思います。
一方、「無農薬栽培」とは、その名の通り農薬を使用しない栽培方法ですが、全く農薬を含まない農産物はほとんどないと言っても過言ではないと思います。実際には土壌中に残留農薬があったり、周辺の畑からの飛散の可能性もあります。無農薬の厳格な基準や認定機関がないので、現在は「無農薬」と表示すること自体が禁止されているようです。減農薬という用語も、何を基準に減量しているのかの基準も認定機関もなく、あいまいな用語です。しかし、「特別栽培米」は、基準が定められた栽培法です(細かな規定を省略すると、その地域で使われる農薬成分の50%減で、窒素(N)施用量も50%減が主な基準です)。
ちなみに、有機JAS規格で使ってもいい無機肥料はいくつかあります。天然由来あるいはそれに準じる事と限定してはおりますが、植物の5大肥料要素であるカリ(K)、天然リン(P)、石灰(Ca)肥料など天然由来の無機化合物も含まれます。また、養鶏、豚糞、牛糞肥料(主としてN肥料)などに含まれる抗生物質(必ずしも天然物ではなく化学合成物でも)は、議論にあがりません。
農薬では、展着剤(化学合成物)、除虫菊から抽出したピレスロイド、性フェロモン、エチレン(バナナなどの追熟用)、ボルドー剤調整用の硫酸銅(Cu)などを使っても有機栽培として認められるようです。「人工的な化学物質を使わない」と定義される有機栽培本来の意味から外れるものもありそうな気がします。余談ですが、種無ブドウ(3倍体ではなく)にはジベレリンという植物調節物質(植物が天然に持っていますが、人工的に作ると農薬です)に房を浸漬して作り出されます。ですから、シャインマスカットなどで「無農薬ぶどう」という表現はないはずです。
少なくとも、「有機栽培=安全」神話については、一考の余地があるのではないでしょうか。下記に参考資料を示します。
表1:生産局農業環境対策課 平成21年6月「有機農業の推進について」より転記
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html 農林水産省JAS公式サイト
https://www.sangyo.net/contents/myagri/organic-cultivation.html
https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/know/chemicals_01.html
有機栽培が良いと言われる第1点は、緩効的な肥料効果だと考えられます。有機肥料がそのまま植物にに吸収されるとお考えの方がいると思いますが、植物は無機化合物しか吸収できないと言われています。「アミノ酸が入った肥料なので・・・収穫物がおいしい」というような宣伝も耳にしますが、現在の土壌肥料学会では、まだアミノ酸など大きい分子を植物は吸収できないと考えられています。有機物は土壌微生物によって分解され、無機物となって初めて植物に吸収されるので、肥料要素の吸収がゆっくりです。つまり、植物の三大肥料要素である窒素(N)、リン(P)、カリ(K)はすべて、アンモニア態(NH4)や硝酸態(NO3)の化合物として、あるいはリン酸(PO4)やカリ(K)イオンとして与える無機肥料となんら変わらないという事です。違うのは、様々な生物の力を借りて無機化するのに長い時間を要するので、少しづつ無機肥料が吸収される点です。
有機物施用効果の第2点目は、土壌に供給する有機物が食物連鎖となって、実に多様な土壌生物相を育て、結果的に土壌物理性をも改良することです。有機肥料は、たい肥、鶏糞、牛糞、豚糞などの形で与えられますが、土壌中に生息する糸状菌、バクテリア(細菌)、昆虫など様々な生物の食物連鎖で、大きな分子の塊である有機物が小さな分子になる循環環境を作り出します。
多様な生物相の棲み処としての土壌は、団粒構造を持ち水分やミネラルなどの保持にプラスに働く物理性改良の効果に貢献します。有機物分解過程に携わる菌、細菌などは腐生性が高く、植物を宿主にする病原菌のような悪さをしませんし、有益な菌の繁殖により病原性のある菌類の繁殖を抑える(拮抗作用=病気にかかりにくい)環境を整えます。また、食物連鎖環境が整備されれば害虫の天敵(捕食者)が増える効果も期待できます。この多様な生物相は、化学肥料一辺倒では実現しないと思います。
有機農業を一方の対局とすれば、化学肥料のみの栽培は別の対局と捉えられます。有機肥料や化学肥料も農薬も否定しない農業は、両極の中間に位置すると考えられます。現実的にはどこにバランス点を求めるかではないでしょうか。昔も今も農業労働の中で大きな比重を占めるのは除草です。水田を例に挙げれば、ヒエをはじめとする水田でも生育する雑草取りは、水田中を中腰で動く女性たちの重労働でした。除草剤の登場は重労働にあえぐ女性たちを解放する画期的な技術でした。除草剤化合物は、植物特有の光合成阻害などを利用しているので、動物には害のないレベルのものです。
除草剤悪者説の誤解は、かつてアメリカ軍がベトナムで使用した2.4-Dの催奇性(実際には不純物であるダイオキシンに由来する催奇性)に端を発しており、「農薬は危険」の誤解が、レイチェル・カーソン著の「沈黙の春」(Silent Spring)によって増幅されました。彼女が指摘したDDT(塩素系化合物)の発がん性への警鐘がよく知られています。現在では、1950年代の科学に基づく彼女の指摘は、必ずしも正しくない事が示されつつあります。しかし、少なくとも土壌残留性の高い塩素系農薬が禁止されるなど、その後の環境政策に与えた貢献は大きかったと思います。現在各国で使用される農薬は、その人体に及ぼす安全性を始め、副作用がない方向にシフトして開発が行われており、有効濃度も数十年前はppm単位だった所から、ppb単位(ppmの1/1000)と低濃度で、しかも種特異性が高いものが市販されています。かつてより、過剰に危険を恐れなくてもよいものが多くを占めるようになり、特に日本の農薬安全性基準は世界でもトップレベルの規制値になっています。
農薬は、植物の薬であり、同じ生物である人間が寄生虫にかかったり病気になれば薬を処方されるのと同じように、植物の病気や害虫に処方される薬です。十分注意して使う必要はありますが、過度に危険視すべきではないと考えます。薬は毒と表裏一体と言われるものですから、正しく理解して使うべきであり、消費者の方々も不確実な情報をもとに過剰な反応をするのも慎むべきです。
有機農業が0.2%ほどに留まる現状を考え、無機肥料や農薬を否定しては99%の生産が成り立たない現実を受け入れ、世界人口を十分養える農業食料を目指すべきではないでしょうか。
エンド・ファームでは、小さいながらもお客様という消費者の食料の一部を担う責任を感じ、最先端の知見に基づく混合農業を探りたいと考えています。