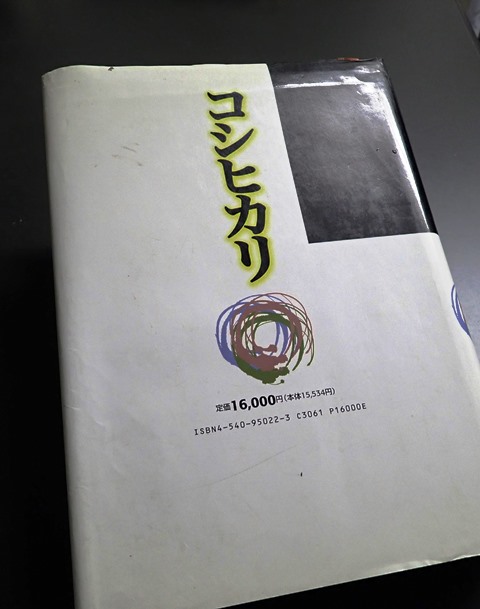
1995年に、北陸作物学会北陸育種談話会編の「コシヒカリ」という本(文献1)が刊行されました。741頁に及ぶ専門書ですが、イネのしかも1品種についてこれだけの内容が紹介された事例は他にないと思います。皆様ご存知と思いますが、コシヒカリは育成当初栽培面積は広がらず、半分やっかいもののような扱いでした。それが、いつのまにかササニシキと並び、ササニシキが衰退方向にある今は、全国で第一位の作付け面積(平成30年 ダントツの35%)を誇っています(文献2)。いったいコシヒカリという品種は何者なのでしょう。
コシヒカリは、「コシヒカリ物語」(文献3)に"七不思議"として語られる通り、育成途上から波乱万丈の歩みがあり、決して優等生品種ではなかったようです。どちらかというと強運で生き残った系統だったようです。
コシヒカリは、第二次世界大戦終戦の一年前(1944年)に新潟県農事試験場(長岡)で高橋浩之さんによって交配された系統の後代から、福井県で選抜育成された品種です。翌1945年は、日本が降伏した年で、長岡は空襲にあったりしたために交配F1の栽培ができなかったという不運な生い立ちから物語が始まっています。詳しくは、文献1,3に語られていますが、倒伏しやすくいもち病に弱い農林1号を改良するために、倒伏しにくく、いもち病に強い農林22号に、農林1号の花粉を交配するところから産声をあげています。
今では食味が良い事が特徴となっていますが、当初の育種目標に「良食味」は全く念頭になかったようです。
終戦後の1946年に初めてF1が栽培され、F2系統3000個体から65個体(穂が長く、茎が多い)が圃場で選抜され、詳細な調査を経て、最終的に50個体が選抜されています。この中から新潟農試に30個体残し、20個体を福井農試へ送ったと記録されています。1950年にF5系統としてわずか5系統が選抜され、後に307系統がF7世代で越南14号(ホウネンワセ)に、318系統が一年遅れのF8世代で越南17号(コシヒカリ)として残ってゆくことになります。
コシヒカリの味、特に魚沼産はおいしいと言われる味は、戦後の育種目標にはない副産物として天がコシヒカリに授けたと思いますが、その良食味はいったいどこからきたのでしょう。
米の食味は複雑で、人が食する時の食感としか言いようがありませんが、近年用いられている食味計という分析装置は、メーカーによって数値化の寄与率に差があるものの、タンパク質量(90%程度)、水分量(数%)、アミロース量(2-3%)前後の数値で決めているようです(某メーカーさん談)。実際には、近赤外線を玄米あるいは白米に当てて得られる数値と、先のタンパク質等の実測値で検量線を作成し、含有量を決め、さらにそれぞれの寄与率を加味した回帰線から食味値(100%が最もおいしい)を求めるという方式だと思います。
よく、おいしい米はアミロース含量が低いといわれますが、日本の食味計におけるアミロースの寄与率はかなり低いようです。世界のコメの中で比べると、日本のおいしい米はアミロース含量が低いです。しかし、日本のコメの中で比較すると、同程度のアミロース含量であってもおいしさは異なります。日本で使う食味計は、あくまで日本のコメの中での食味を数値化したものであり、そのほとんどはタンパク質含有量と水分値で決まるようです。
ちなみに、エンド・ファーム栽培のコシヒカリ(2009-2020年)をJA大北で使用する食味計で測定した結果、(y = -5.5939x + 109 R² = 0.9449 n=104 y=食味%、x=タンパク量%)という高い負の相関が得られています。つまり食味計の95%程度はタンパク量で決まっているという事で、タンパク量が7%以下4%位の間で低い方が食味計の値は高く出ます。
とはいえ、食味計の数値に現れない味はカウントできませんので、官能試験といって実際何人かのパネラーが実際に食して、調査項目毎に標準米(コントロール)と比較する方法が使われています。だいぶ味の数値化ができてきたとはいえ、日本人の好む味というものは、なかなか複雑なようです。中国広東省とかインドやベンガル地域では、パサパサの味を好む人が多く、日本のコメは粘りすぎてまずいと言われます。所変われば好みも変わります。
日本人が感じるコシヒカリの味の良さがどこから伝わったのかは大変興味深いです。コシヒカリの祖先品種のつながりを調べた2017年の論文(文献4)によると、コシヒカリと同程度の味の良さは、「旭」という品種に認められるようです。しかし、その子孫品種にはコシヒカリを超える良食味が見つからないという不思議さもあります。平均的にみると「旭」から続く農林22号までの母系系統でコシヒカリに近い数値が多かったようですから、やはり「旭」のおいしさがコシヒカリに繋がっていると考えられます。
日本のコメは、世界の米品種の中では、「粘り気のある」という言葉でくくられる程均一で、どれもおいしいと思います。食料が不足し、飢えを抱える国ではまだ質より量が優先されます。味が良い米というのは、贅沢な幸せです。日本では、いまだにコシヒカリを超える味はないともいわれ、コシヒカリ偏重を批判する向きもあります。各県で様々な品種が生み出されていますが、コシヒカリの血が入らない品種はないといっても過言ではないでしょう。
エンド・ファームでは、ささやかな贅沢としてコシヒカリの味を選び、仁科の里の土と自然にあった作り方で提供できれば十分と考えています。賛同いただけると幸いです。
コシヒカリのずっとずっと昔のイネや、野生のイネは泥が十分にある沼地に自生しています。決して、清らかな水が流れる砂地が自生地ではありません。ススキなどもそうですが、水生のイネ科植物は泥を好みます。言い換えれば、イネの本性に近く栽培するには泥、すなわち粘土質が適度にある土があっています。新潟県の魚沼地域はその字のごとく沼が多い土地柄です。おいしいと言われる魚沼産コシヒカリは、魚沼の泥土で栽培されるからではないでしょうか。
一説によると、「仁科」は"粘土質で段丘の場所"を意味するそうです。長野県には「科」の字がつく地名が多いです。ここ仁科の里は、確かに粘土質の土地柄で、高瀬川の砂地とミックスされた土がベースになっています。清流と粘土のバランスが、おいしい米を作りだす一因かもしれません。味わってみてください。
文献1:「コシヒカリ」 北陸作物学会北陸育種談話会編(1995) 農山漁村文化協会.
文献2:「平成30年産 水稲の品種別作付動向について」平成31年4月11日資料(2019) 公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構.
文献3:「コシヒカリ物語」 酒井義昭著(1997) 中公新書 中央公論社.
文献4:「コシヒカリ」祖先品種の栽培特性と食味 中岡史裕ら(2017)北陸作物学会報52:55-59.
余談ですが、コシヒカリBLという名前を聞いたことはあるでしょうか。コシヒカリにいもち病抵抗性遺伝子を入れた系統(BL: blast resistance lines)という育成系統で、主として新潟県、富山県で栽培されているようです。コシヒカリBLもコシヒカリと表示してもよい事になっているので、先の栽培面積日本一(文献2)の中にはコシヒカリBLも含まれています。育種的にはコシヒカリIL(isogenic line:同質遺伝子系統)に近い定義ですが、単一遺伝子を導入した系統が同質遺伝子系統ですから、BL系統はIL系統とは若干異なるようです。同質遺伝子系統は、コシヒカリにいもち病抵抗性遺伝子など1遺伝子を入れたものと定義されるので、理論的には他の遺伝子はコシヒカリとほぼ同じといえます。見かけはほとんど区別できないでしょう。耕し人がかつて、イネ白葉枯病抵抗性の(準)同質遺伝子系統の研究に携わった経験からすると、異なる遺伝子が入っているコシヒカリ(BL)が、純正コシヒカリと同じ味とは言い切れないと思います。もっとも、純正コシヒカリという品種も、長年違う土地(違う県など)で栽培されていると、その土地にあった遺伝子群が優位になるので、必ずしも全く同じとは言い切れないでしょう。恥ずかしながら、コシヒカリBLもコシヒカリであるとは、つい最近(2020年)まで知りませんでした。
参考:Wikipedia "コシヒカリBL"
私どものような個人経営では、自分たちの人件費を計算するととんでもない赤字になります。自分たちの労働を【ゼロ】扱いにして、ようやく農業所得数万円です。エンド・ファームでは、年金が生活費で人件費の穴埋めをしているというのが実情ですので、赤字でなくなる米の価格設定をすると今の値段の何倍になるのかわかりません。しかしながら、資材費の値上がりや運送業者さんの値上げの中で、若干の値上げをさせてもらわないと、人件費を無視しても赤字ギリのラインに来ております。お客様には、この点をご理解いただきご協力をお願いする次第です。
巷でやたら高い価格になっている米は、おおざっぱにみて、【農家の庭先価格→各JA定額手数料→全農%手数料→中間卸(重層構造)→小売りの取り扱い手数料】で売られるルートが主力です。2024年は農家庭先価格も全農系で値を上げて頂いたようですが、高騰した米価のどのくらいを占めるのでしょう。どこかで誰かがうまみを得ているのでしょう。
大型経営の農業生産法人は、人件費を計上して法人としての利益を出していると思いますが、補助金ありきが前提で、大型機械とオペレーターの人件費でギリギリの経営だと聞いております。補助金なしではやはり赤字になるのではないでしょうか
シミュレーションが得意な知り合いの話ですが、某ゼネコンを退職して実家の農家をやろうとして、どう計算しても儲かる図式が得られないとの計算結果で、農業をギブアップした方がいます。今の貨幣経済価値でみると、これが農業の現状だと思います。しかしながら、幸福感のような別の価値観でみると、時間と労働を売る事もなく、空気や水のうまさ、自由さ(完全フレックスタイムが可能)などを満喫している生活そのものは途方もない金額を稼いでいる事になるでしょうから、こんな贅沢をしていいのだろうかと幸せいっぱいになる一面もあります。
米の価格は、政府の言うように大型化しても土地が狭い日本では、その恩恵が価格には跳ね返らないでしょう。世界のどの国でも農業に補助金を出しておりますので、広い土地を持つどんな国でも補助金なしで成り立たないのが農業なのでしょう。ならば、エンド・ファームでは、幸福度の高い経営を目指したいと思っております。
高騰する新米価格ですが、100万トン以上の備蓄を抱える国が備蓄米を放出すれば米の価格は上がらないはずです。ふと感じた疑問ですが、政府備蓄米はどこの倉庫に保管しているのでしょう。Wikipediaによると、備蓄米は主食用には出さない事になっているそうですが、【JAなどの政府寄託倉庫にて低温保管され、大凶作や不作の連続などにより米の民間在庫が著しく低下するなどの米不足が発生した際に放出される】とあります。そうであるならば、日銀の市場介入のように今回の高騰時には米を放出してもいいのではないかと思います。自腹で倉庫を作って運営する代わりに、全農-単協(JA)の倉庫を借用すれば倉庫費用はかなり安く抑えられるはずです。それとも、莫大な対価を倉庫の所有者に支払っているのでしょうか。癒着構造をも想像させますが、政府一体となった米価コントロールの側面は否定できません。農家サイドとしては、米価(農家庭先価格に反映する)が上がったほうがありがたいのですが、個人的には主食であるコメを必要以上に高く販売する事には反対です。消費者あってのコメ販売です。
こんなですから、年金農業者としては、食べて生きていけるだけの米の対価を頂ければ十分です。世間程ではなく、若干の値上げは検討させて頂くかもしれませんが、エンド・ファームでは、現在の価格を維持したいと思っております。今後とも、よろしくお願い致します。